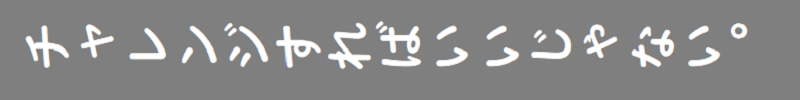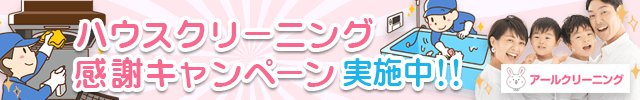お正月、ブックオフで文庫本の新春セールをやっていた。私が以前から気になっていた時代小説は在庫が潤沢にあるらしく、安売りコーナーで全巻揃う上に、さらに新春セール値引きとあって、まとめて計13巻を買ってきた。
あきない世傳 金と銀
以前、「みおつくし料理帖」という時代小説を身内から勧められ読んで以来、私は機会があればもっと高田郁(たかだかおる)の小説を読みたいと思っていた。年始に立ち寄ったブックオフで高田郁の「あきない世傳 金と銀」を見つけ、かなりお買い得な値段で全巻入手するに至ったのである。
この「あきない世傳 金と銀」という本は、江戸時代の中期を舞台にした商いの話で、それはそれはとても面白いのだが、その時の時代背景をも各所で学ぶことが出来る。私がいままでになんとなく聞いた言葉が持つ意味なんかも、改めてこの本を通して学べるのだ。
この本はドラマ化もされているらしいが、ドラマや映画では恐らく随所にある細かな説明は端折られてしまうに違いない。そして、大筋面白い話としてドラマや映画でもストーリーを楽しむことはできるだろうが、豊かで読み応えのある内容を考えると本でなければ勿体ないと思うのである。
士農工商の暮らしを知る
この本の主人公の父親は士の血筋で、学者であり私塾の先生である。その父親から、「商いとは、即ち詐り(あきないとは、すなわちいつわり)」という教えを受けて育つ。父親の教える私塾は田舎にあり、その地域の豪農によって支えられて運営されているということだった。
田舎に住む学者である父は、「商人とは汗水掛けて作ったものを右から左に流すだけで金儲けをするとはけしからん!」という考えの持ち主だったのである。主人公である娘は事情があり、呉服商へ奉公へ出て、「商いはいつわりではない」ということを学び、商いを学び楽しみながら成長するという話である。
この本を読み、士である武士について殆ど知ることはないのだが、どの時代にも金持ちが存在しているということは再確認した。そして、普通の民間人は百姓も、職人も、商人もみな苦労をして生きていることが伺える。改めて、江戸時代中期にあったそれぞれの暮らしを知ることができたことは幸いである。
教科書から消えた士農工商
勉強を殆どしたことのない私も、士農工商という言葉は、小学校の高学年の時に昔の日本の社会階級として学んだ記憶がある。しかし、現代では実は「士農工商」が社会階級ではなかったということが分かり、教科書から撤廃したというから驚きである。
何十年もの間、学校で社会階級と教えていたものが誤りだったとは!その何十年もの間、「これは間違っている」と言う学者の申し出を誰も真に受けなかったということなのだろうか?長年に渡り、「士農工商」はテストによく出題されるほど、公の事実としていたことに愕然とする。
江戸時代中期には殆どの人の職業がこの士農工商という枠に収まっていたのは事実だろう。それなら階級という部分だけを是正すれば良いと思うが、そっくり「士農工商」が撤廃されたことに私は違和感を持つ。今、学生の若者達は「士農工商」という言葉を知らずに育つのかと思うとなおのことだ。
奉公人に支えらる社会
私が読んでいるのはフィクションストーリーには違いないが、こういった物語はその時代背景を調べた上で作られた作品であることは間違いないだろう。
この本を読んでいると、江戸時代中期の商家の人達や、その周りに関わる人の暮らしぶりまで細かに知ることが出来る上に、楽しみながら教養を得ているような気になれるのもこの本の良い所である。
この時代の店主と、その家族と言われる人達は主筋といわれ、その店をで働く人達は大多数が住み込みの奉公人だ。そして主筋と奉公人には明らかな格差が存在する。しかし、奉公人は現代社会程に自分の権利などは主張しない。
そういう時代なのだと言われれば、それで話は終わりだが、奉公人の多くが真摯にひたむきに働き、主筋と協力し合って商いに精を出すことが特別ではないことだったのだと伺える。主筋だろうが、奉公人であろうが友に商いを盛り上げようとする姿勢に古き良き日本の素晴らしさが潜んでいるように思う。
とにかく食うのに困る時代だ。奉公人になれば雇い主が衣食住を与えてくれて、毎日3食にありつける。それだけで、どれだけ恵まれている日々であるかという話だ。10歳になる前に奉公人になる人が多くいたことを考えると、私が子供だった4~50年前さえ、本当に恵まれた暮らしをだったと痛感する。
買うての幸い、売っての幸せ
この物語のストーリは、商売についてである。主人公が働く商家である五鈴屋にはモットーがあり、それは「買うての幸い、売っての幸せ」である。
五鈴屋では、確かな品を適正な値段で客に売り、客に喜んでもらいつつ、売り手としてその喜びに預かり、少しの利を貰い受けるという姿勢なのだ。 なかには暴利を貪るような商家も多数く存在しただろうが、長続き続きする商家は、客に喜んでもらえる商売をしていたことが伺える。
主人公が奉公人として働きだした頃の五鈴屋は、経営が厳しい状況だった。そこから幾つもの試練を乗り越えアレコレ知恵を絞り、店が少しずつ大成長するストーリーには魅力がある。厳しい状況の時に店主が率先し知恵を絞り、奉公人と一つになって商いを成長させている様子はビジネスの鏡だ。
加えて五鈴屋は関わる商売仲間だけでなく、独立して働く行商を含め、職人をも大事にし、全員が適正な対価を得られるように相互協力をして成長するのだ。現代に欠けてしまった人情に厚い、一生懸命働く人々の話なのである。
現代社会の企業で目の当たりにする自己中心的な働き方や、企業のコストカットの影響による製品やサービスの下落、そして取引先の利を奪うような状況を考えると、私たちは今一度この「あきない世傳 金と銀」から学ぶことは多くあるのではないかと思ってしまう。